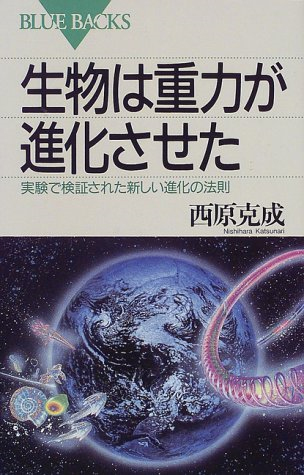 宇宙から還った向井千秋さんは、無重力の宇宙から地球に帰還するとき三分の一G(地球上の重力の三分の一)を境として自分の体重がズシリと重くのしかかってきた、と話している。ふだんはつい忘れがちだが、われわれは地球の一Gという重力環境で生きている。地球上に存在するあらゆるものには、一Gという重力があまねく作用しているのである。そもそも、われわれが地球の表面にへばりついて、宇宙のはるかかなたまで飛ばされないのは重力のおかげである。
宇宙から還った向井千秋さんは、無重力の宇宙から地球に帰還するとき三分の一G(地球上の重力の三分の一)を境として自分の体重がズシリと重くのしかかってきた、と話している。ふだんはつい忘れがちだが、われわれは地球の一Gという重力環境で生きている。地球上に存在するあらゆるものには、一Gという重力があまねく作用しているのである。そもそも、われわれが地球の表面にへばりついて、宇宙のはるかかなたまで飛ばされないのは重力のおかげである。
この地球上で生れた生物が、この重力の影響を受けないはずがない、と考えるのは当然であろう。一九〇一年、ドイツの発生生物学者ルーは、生物に対する重力の作用の重要性に着目しバイオメカニクス(生体力学)という学問を創始した。くしくもアインシュタインが、光に波動性と粒子性の二つの性質があることを発見し、のちの量子力学の端緒をひらいたのもこのころである。
ルーは、個体発生と系統発生の関連性の研究で有名なヘッケルの一番弟子であり、重力の作用を中心にすえた生体力学的な発想によって進化の法則を明らかにしようと試みた。しかし、時のドイツ生物学会で力をもっていたのは、医学者と童子に政治家でもあったフィルヒョーであり、彼は進化とは「何億年も前に起こった検証不能の夢物語」であると断じ、それ以降、進化については真摯(しんし)に研究しようという雰囲気は一掃されてしまった。
第一次世界大戦が終わると、戦勝国イギリスの科学思想が世界を席巻した。イギリスで生れたダーウィンの進化論はこの 流れに乗り、いくつかの修正をほどこされて、現在も「正統」進化論(ダーウィニズム)として君臨している。その根本概念は依然として「突然変異」と「自然淘汰」である。そして、今やその研究の根幹は、古生物学でも、動物学でも、もちろんルーのバイオメカニクスでもなく、今日隆盛をきわめる分子生物学なのである。
分子生物学は、今から五〇年ほど前に、バクテリア(細菌)やファージ(細菌に寄生するウイルス)を使って、遺伝現象を解明する目的で始められた。しかし、このバクテリアは、なんと1万五000G(地球上の重力の1万5000倍)に耐えられる代物なのである。超音速ジェット戦闘機のパイロットが、急上昇するときに四Gから五Gを受けると失神しそうになるという話を聞いたことがあると思う。1万五000Gにも耐えられるバクテリアと、五Gで死んでしまいかねない人間を初めとする脊椎動物を、はたして同列にあつかってよいものなのだろうか。
本書は、生きとし生けるものすべてを対象に進化の法則性を明らかにしようとするものではない。単細胞生物も多細胞生物も、植物も動物も、昆虫も脊椎動物も、あらゆるものをごちゃまぜにして進化が語られてきたあこれまでの進化論をとにかく整理し、われわれヒトを含む脊椎動物の進化に限ってその法則性を明らかにするものである。
ダーウィニズムデは完全にブラックボックスになっている個体発生と成長の過程をくわしく観察すれば、脊椎動物の進化は「突然変異」と「自然淘汰」などで起こっているのではなく、明らかに重力を中心とした力学対応で起こっていることがわかる。また、長らく進化の論争の争点になっている「獲得形質が遺伝するか」という問いに対しても、行動様式というソフトの情報さえ伝えられれば、獲得形質を次代に伝えられることがわかる。つまり「遺伝」によらずとも獲得形質は次代に伝えられるのである。
筆者は、これらの進化の法則を、系統発生の或るステージに在る動物を用いて実際に進化を起こさせるという実験を通して検証した。これらの実験は意外にも簡単で、再現可能である。
今、医学では治らない病気が増えている。この大きな理由は、ダーウィニズムの観点からわれわれの体を考えてしまっていることにある。原始脊椎動物からヒトの体までが連続的に変化していることを念頭に置いていないので、病気の原因がわからなくなってしまったのである。
進化の問題は、小・中・高校時代から大人になっても、誰でも等しく興味をもちつづける数少ないテーマである。進化といえば反射的に「突然変異」と「自然淘汰」が出てくる人もいれば、すべての生物進化をこの二つの概念で片づけてしまう「正統」進化論に悶々とした疑問をもっている人も多いと聞く。本書は進化に関心のあるすべての人に読んでもらいたい。そして、今一度、すべてを白紙にもどして脊椎動物の進化について思いをめぐらせていただきたい。
最後に、本書をまとめるにあたり数々のご指導をいただいた講談社の堀越俊一氏に深く感謝する。
一九九七年一二月 西原克成
講談社ブルーバックス/¥800(税別)/1997

