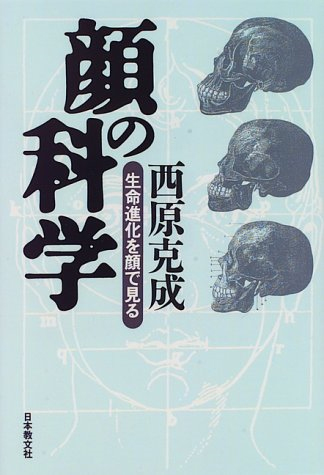●「顔」と進化の謎
脊椎動物の「進化の謎」を解(と)くには、「顔」の成り立ちを研究することが最も適している。顔の中には、この宗族(そうぞく)がたどってきた進化の歴史がすっぽりと納まっているからである。
この宗族の源となる生命の形は、鰓孔(えらあな)のある口の嚢(ふくろ)をもったムカシホヤという脊索類(せきさくるい)-半索類-をその出発点としていると考えられる。原始の生命体では、この鰓孔のある口の嚢が、その身体の主要部分を形成していたのである。
この生命体が、幼生(ようせい)のまま成体となって、頭方向に向かって進むようになると、長い時間を経過するうちに、力学対応によって、顔(頭部)・頸部・胸部・腹部の四つに分化することになるのである。
「顔」は、太古の”生命体の基本体制”を、今日の人類に至るまで保っている”生命の要(かなめ)”であり、いわば”生命を代表する器官”であると考えることができる。
力学を主導とする進化の概念は、ラマルクにはじまる。用不用説がこれである。この流れはやがてヘッケルへと受け継がれて大きく飛躍した。しかし、これは遺伝学が確立される前のことであったので、後に本末が転倒するほどの混乱が生じた。
ヘッケルの高弟ルーは、進化の原因は重力などの力学にあるという確信をいだき、のちに生命発生機構学(せいめいはっせいきこうがく)とともに生体力学(せいたいりきがく)-バイオメカニクス-の分野を創始した。しかしこの学問もまた、その本質が、長期にわたりほとんど理解されないまま今日に至っている。
そのため、個体発生(こたいはっせい)と系統発生との相互の関係に対する解釈は、今日においても依然として混乱が続いている。その理由は、あらゆる自然科学の基礎となる”力学的な世界観”と、それに付随する、自然界における”因果の法則”とが、生命科学の中に正統に導入されてこなかったからである。二十世紀も終わろうとしている現在でも生命科学(生物学)は混迷の真っ只中にある。
●忘れられた力学
現代の医学と生物学には、重要なことが”忘れられ”ている。「力学」の正統な導入である。 現実の世界では、力学的な世界観というのは、老若男女を問わず、あまねく世界に行き渡っている。あらゆる生活基盤が、古典的なニュートン力学の上に成り立っているという常識を疑うものは少ない。
しかしこれが生命現象となると、とたんに重力や力学作用が忘れられてしまうから不思議だ。この領域における力学というのは「生体力学」のことである。生体力学は、100年前にルーによって創始されたが、今日これがほとんど基礎的な生命科学のなかで定着していない。現在、宇宙で無重力の実験が散発的に行われているが、これらは約80年前に中断しているルーの生命発生機構学の延長線上にないのである。
これは今世紀の医学者や生物学者が、微細構造の研究のみに奔走し、”肉眼による形態学的研究”を極度に軽視したためである。習慣などによる体の使い方の偏りなどの、生体力学によって生ずる細胞レベルの変化は、外傷を除けば、すべて正常な細胞のリモデリング(改造)であり、顕微鏡で把握される病理組織像を一切示さない。にもかかわらず、生体力学によって病気が発生するのである。これは肉眼レベルの骨格の変形や移動が原因で起こる疾患だからである。
●シュレーディンガーと分子生物学
分子生物学という学問は、今から約50年前、理論物理学者であるE・シュレーディンガーの著書”What is life?”(邦訳『生命とは何か』・岩波新書)に端を発している。もともと生物学にはまったくの素人だった彼が、当時の生物学の混迷に対し、見るに見かねて、物理学的手法による生物学の本質的現象の解明を提唱したものである。
これに呼応して、当時物理学に行き詰まっていたデルブリュックら若い研究者が、米国のコールドスプリングハーバーに集まって、ファージとバクテリアを用いて、遺伝学の分子レベルの解明に取り組んだのである。
こうして今日の分子生物学と分子遺伝学の隆盛が築かれることになるわけであるが、波動力学の体系を立てたシュレーディンガーが、実際に研究に携わったわけではなかったので、ヘッケルやルーの生物学の根幹を成す「力学」の導入を忘れてしまったのである。
臓器の力学的な相関性が働くのは、多細胞動物においてである。彼らが用いたファージやバクテリアでは、生体力学作用のほとんどが無視できる実験系であることに気づくのに50年を要したのである。
●生命の形態学
ところが意外なことに、すでに30年前に、この力学的世界観にもとづいて、ヘッケルの生命発生原則を、脈管系の個体発生と系統発生との比較によって、みごとに検証していた形態学者がわが国にいたのである。
東京芸術大学教授であった故・三木成夫(解剖学)である。三木は、医学を修める前に工学を学び、当時最先端の科学であった航空工学を学んでいた。三木が芸大の講義録として遺(のこ)した膨大なシェーマ(図解)の中には、ルー、ヘッケル、ゲーテ、ラマルク、キュヴィエ、リンネの系譜がすっぽりと納まっていたのである。
本書は、この三木成夫の「生命の形態学」にならって書き進めたものである。ということは、ゲーテの形態学、ラマルクの生物学、ヘッケルの生物発生原則��系統発生学、キュヴィエの器官の相関性、リンネの分類学などの学問の系譜を受け継ぐものであり、さらにそれらの形態学と生体力学、分子生物学、分子遺伝学を統合した、古くて新しい二十一世紀の生物学のさきがけとなるものである。
●ネオ・ダーウィニズムの盲点
体力学の研究は、古典的な肉眼による研究と、その背後にひそむ微細な構造を視覚で観察する研究とをもってしても、ただ形態学のみでは把えることのできない現象の研究であり、従来の多岐に分立していた形態学、生理学、生化学、遺伝学、分子生物学などの学問を、力学の視点を導入して統合しなければ、解明の困難な領域である。
しかし生命の形態学の流れを調べてみると、生物の進化の原因が、重力をはじめとする力学にあることが、すでに200年前にラマルクによって記されている。また90年前にはカンメラーの実験によって、これが検証されているのである。
これらがイデオロギーによって抹殺され、忘れられるという悲劇の歴史が今日に至るまで続いている。二十世紀においてはラマルクとヘッケルを検証しようとすれば、学問界では抹殺されたのである。その理由は、ネオ・ダーウィニズムに抵触したからである。
生物学や医学の法則性は、すべて詳細な観察にもとづく経験の蓄積から得られた法則性、つまり経験則で成り立っている。これを生化学的、生理学的に、あるいは数理的、電気的、力学的、分子機械学的に検証するのが、今日的な生命科学の手法である。
ところがダーウィニズムとネオ・ダーウィニズムには、どこにもラマルクのような観察にもとづいた法則性がない。この思想の源のウォーレスは、観察は行ったが成体のみを扱っていたために、生長過程をいっさい考慮せずに、マルサスの人口論から借用した「生存競争」という人類にのみ特有の論理を当てはめたのである。ダーウィニズムは、最初から社会学を出発点としていたのである。
つまりマルクス経済学と同様に、想像にもとづくイデオロギーであったのである。個体発生の過程がいっさい無視され、さらに成長の過程すら考慮されておらず、成体となるまでの過程がいっさいブラックボックス状態となっていたのである。「発生過程の変化なくして、形態の変化はありえない」(養老孟司)ことは論ずるまでもないことである。
後に詳しく実例をあげて説明するが、高等な脊椎動物においては、仔は親が教育しなければ育たないのである。従って、仮に高次に進化した動物が、彼らのいうように突然変異で生まれてきたとしても、親はその育て方を知らないから、その仔は必ず捨てられて死ぬことになるのである。
突然変異では、その名が示すように奇形と分子病、つまり変異しか生じない。これを生かして育てられるのは人類のみである。人類は、これを標準に近づけて育てる。つまり手術したり、遺伝子治療をほどこすのである。このような簡単なことが、150年間忘れられていたのである。
また突然変異で生まれた新しい形質は、交配により数代の間に稀釈されて標準型に吸収されてしまう事は、ヴァイスマンの時代の90年前頃からわかっていた。従って突然変異で形が進化するとしたら、相当大量の個体が一斉に変異をおこさなければならないことになるのである。
もとよりこれらのことに気づいた研究者もたくさんいた。しかし彼らは、宗教裁判を受けたガリレオのように「それでもラマルクとヘッケルは正しい」と確信しながら、二十世紀の「暗黒の中世の生物学」の中で抹殺されて行ったのである。
●ものの本質
もう一つ、この領域で忘れられていることがある。それはこの領域の研究対象の「本質」についてである。現在の研究というのは、この本質の探求をはずして、いきなり分析的に微細なことがらに取り組む。
DNAや遺伝子、分子、細菌、特殊な細胞、特殊な器官などについてはよく調べるが、生命システムの全体像について、あるいは生命体の原形についてはほとんど考えることをしない。これが現代の西欧流の科学のやり方であり、大きな欠陥を生み出している源となっている。
多くの学者が生命科学に取り組んでいながら、「生物界における脊椎動物の本質を規定する物質は何か」「脊椎動物界における哺乳類(ほにゅうるい)の特質は何か」「哺乳類における人類のみの特徴とは何か」ということを真剣に考える研究者が、ほとんどいないのが実状である。
また、本書の主題である「生命とは何か、進化とは何か、遺伝とは何か、免疫とは何か、顔とは何か、歯とは何か、骨とは何か」ということを本質から考える人も、昔の大学者を除けば、近年ではほとんどいない。その点でも、リンネ、ラマルク、キュヴィエ、ゲーテ、ヘッケル、ルー、三木は偉大であった。
本質に対する疑問すら抱かないのであれば、生命科学の謎は解けるはずもないのである。
さいわい、日本人は、かつて生命の本質である魂が何にゆらいしているかを直感的に知っていたらしい。ヘッケルが気づく2000年も前から、彼の生物発生原則の源となった胎児を模した勾玉(まがたま)を、いのちと魂の象徴として、わが国では、代々皇祖皇宗の守り神として受け継いで今日に至っているからである。
西欧流の科学が、わが国に本格的に導入されてから120年、またわが国が米国に占領されてからはや50年が経過した。
そろそろみずからの伝統に則って、世界をリードすることのできる、本質から離れることのない生命科学を、わが国の主導のもとに、再構築する機運が満ちてきたように思われる。
この時を告げるのが本書の役割の一つでもある。
日本教文社/¥1,648(税別)/1996
●書評:立花 隆氏
西原克成『顔の科学』は、知的にチャレンジングな本である。
西原は、ダーウィンの適者生存論は、マルサスの人口論など当時の社会学に影響されたイデオロギー的見解であって、本当の進化論を説明していないという。ダーウィニズムは突然変異と自然選択で進化を説明しようとするが、現実には孤立した突然変異は種の中で整理されてしまって生き残れない。突然変異で種の進化が起るためには、相当大量の突然変異が一斉に起こらねばないが、それはダーウィンの理論では説明できない。
西原が進化の真の要因としてあげるのは、重力などの力学的作用である。環境変化に対して生物が力学的な反応をすることによって、生体力学(バイオメカニクス)的な変化が起き、それによって形態が変化していく。その変化の様子は、系統発生学の脊椎動物五億年の形態的歴史の中に刻みこまれており、なかんずく顔の歴史の中に、その進化過程がすっぽりおさまってるといい、脊椎動物の最古の祖先であるムカシホヤから「顔の歴史」を語っていく。この部分はなかなか面白い。新しい生物史の見方を教えてくれる。
あらゆる自然科学の基礎には、力学的な世界観があるはずなのに、生物学の進化論では力学が無視されてきたのは、イデオロギーが邪魔してきたからだという。
なるほどと思う部分とそうかなと思う部分がある。